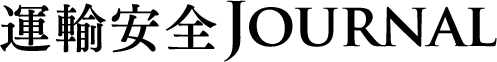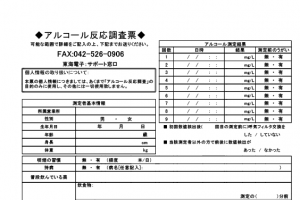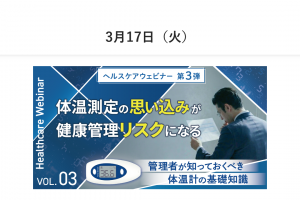北海道飲酒運転根絶条例に追加を提案。18条にアルコール依存症治療、19条にアルコールインターロックの義務を。
2025.11.27
2025年11月20日、東海電子は北海道が主催する「令和7年度 飲酒運転根絶シンポジウム」に参加しました。
当社代表取締役杉本はパネリストとして登壇し、約170名の参加者とともに飲酒運転ゼロ社会に向けた現状の課題と施策の方向性を議論しました。
パネリスト紹介─3名の専門家によるメッセージ

国井氏は、飲酒運転事故の被害に遭った経験から、事故の恐ろしさと交通安全の重要性を訴えました。
2023年、タクシーに乗車中、飲酒運転の車に衝突されました。
「もう少し後部座席寄りにぶつかっていたら命を落としていた」と言われる大事故です。
当時の状況を記録したドライブレコーダー映像が、タクシー会社様の許可を得て公開されると、会場は緊張に包まれました。

桒内氏は、アルコール依存症の治療・回復支援の視点から、依存症は誰にでも起こりうる現実であることを説明しました。「モラルだけでは根本解決にならない」と強調し、検挙された人が適切に治療につながる仕組みの必要性を訴えました。

東海電子は、企業理念である 「社会の安全、安心、健康を創造する」 のもと、アルコールインターロックの社会実装や、アルコール問題を抱える方とその家族への予防支援の取り組みについて紹介しました。
議論の中心は「再発防止と制度化」。参加者からは、アルコール検知器の選び方やインターロック導入後の効果など、具体的な質問が積極的に寄せられました。
東海電子による北海道飲酒運転根絶条例への提案
現在、北海道飲酒運転根絶条例は第17条までが制定されています。
東海電子は、条例に以下の条項を追加することを提案しました。
- 第18条:治療の義務
アルコール依存症や問題飲酒を抱える人に、治療や回復支援のアクセスを義務付ける。 - 第19条:アルコールインターロックの義務
飲酒運転違反者に対し、インターロック装置の設置を義務付ける。
飲酒運転は、技術だけ、制度だけでは根絶できません。
「治療」と「技術」の両輪で社会全体が取り組むことが、再発防止の鍵です。
北海道 2つの飲酒運転事故から学ぶ教訓
北海道には、風化させてはいけない2つの飲酒運転事故があります。
小樽の事故の7月13日が 「北海道飲酒運転根絶の日」 と定められました。
痛ましい事故を未来への教訓に変えるためには、事故の瞬間だけでなく、
その根本原因に目を向けることが必要です。
技術と制度、そして教育という土台で、再発防止の環境を整えることが求められています。
東海電子は今後も、北海道をはじめ全国の地方自治体と連携し、
条例改正やインターロック技術の普及、治療支援に取り組み続けます。
悲しみの記憶を未来への教訓に変えるために。
最後に。控え室でパネリスト記念写真。
国井さま、桒内さま、北海道での飲酒運転防止活動頑張ってください。
是非、条例案追加、発信してくださいませ。

東海電子は、引き続き、日本全国、行きます。
とくに、飲酒運転根絶条例のある都道府県の、「アルコール健康障害対策実施計画」の担当部局の方、くらし交通安全部の方、お声がけください。