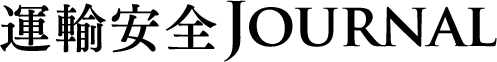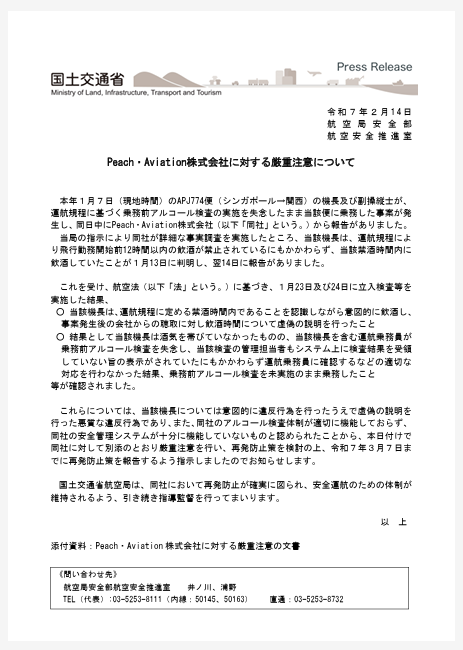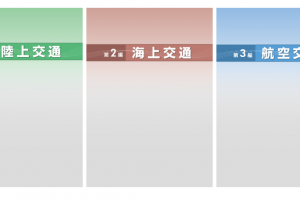アルコール検査規則なんてどうでもいい。パイロットの飲酒規制違反が、再発防止策本命である”AUDIT(アルコールスクリーニングテスト)実施を延期させているならば本末転倒、メンツを捨てて、改正(1)(2)を即日実施せよ。
2025.2.15
異例の事態が起きています。むなしい本末転倒が起きています。
パブリックコメントで「2025年1月」のどこかの日で改正となるはずだった、航空乗組員・客室乗務員向けのアルコール規制の改正が、2月に入っても一向にアナウンスされなかったのです。
時系列で整理します。
○2024年11月22日 国土交通省 報道資料
「航空医学分野の規制等に関する検討会」とりまとめの公表~操縦士の健康管理制度、アルコール検査制度等を見直します~
○2024年12月1日 JAL メルボルン事案発覚
○2024年12月5日 操縦士の健康管理制度、アルコール検査制度見直しパブリックコメント開始
「航空機乗組員の健康管理に関する基準」等の一部改正(案)に関する意見公募について
○2024年12月27日 日本航空株式会社に対する業務改善勧告について
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000268.html
びっくりするような内容ではありますが、規則に基づいて行政処分が決定した以上、内容の賛否はあれど、運輸行政としてはこの話は終わりです。
ですので、
○2025年1月X日 パブリックコメント終了、「見直し版アルコール検査制度」開始~!
となるハズでした。
ところが・・。
まず、ここ5年、本誌では数々の運輸・安全関連のパブリックコメントや法令・規則の改正をフォローしてきましたが、時期が明記されている法令・規則改正が、何の説明もなく延期となるケースは見たことがありません。
かなり、異例と言えましょう。
JALの件が影響しているならば、本末転倒です。なぜなら、航空従事者の飲酒問題把握へ、踏み込んだ改正内容も含まれているからです。(アルコール検査ルール改正のことではありません)
アルコール検査なんて どうでもいい
はい、航空業界は合理化したいのですよね。今のアルコール検査実施要領は煩雑ですから。航空業界も人手不足らしいですしね。
安全管理の仕組みが有効に機能していれば、アルコール検査の回数や頻度はどうでもいいと判断したわけですよね。検討会は。確かに、煩雑だという意見に筆者も同意します。
航空行政・業界の方々、アルコール検査の回数や頻度は、どうぞ好きにしてください。全航空従事者の義務化をやめて、いっそのこと、他の国のように「ランダムテストを受ける義務」にして一気に検査回数を減らしてもいいんじゃないですか。アルコールや管理体制に自信がおありのようですから。
”所詮アルコール検査は水際防止”ですから
今回の改正で、画期的だったのは、アルコール依存症対策の、仕組み化の方だと思う。
そもそも、アルコール検知器を使わなくても済むように、体調管理・健康管理をすべきなのです。水際でアルコール検知器が目的通りの役割を果たすということは、一次予防が機能していなかったということです。この意味で、アルコール依存症という観点で健康管理(フィジカル・メンタル)を捉え直す今回改正はとても意義があると思う。パイロット同士のかばい合いや管理側の不手際とか、あいまいな企業風土の議論よりもずっと実践的な内容です。
改正内容をもういちど見てみましょう。
| 12月のパブリックコメント ②アルコールに関する教育訓練及び健康管理の充実並びにアルコール検査 | ||||
| 改正 | 対象規則 | 改正概要 | 具体的な改正 | 実効性 |
| 改正その1 | 安全管理システムの構築に係る一般指針一部改正 | 安全管理規程に定める事項である「アルコールに関する教育」に関し、教育内容には、「航空医学分野の規制等に関する検討会」のとりまとめ内容を十分に反映させることを求める | ②「航空医学分野の規制等に関する検討会とりまとめ(令和6年 11月22日)」の以下の内容 ⅰ)航空機乗組員及び客室乗務員の自己管理の徹底 (例) ・アルコールの基礎知識(酔いのメカニズム、アルコールが心身に及ぼす影響、飲酒の適切な量及び頻度等) ・過去の飲酒事案(経緯、原因、再発防止策等) ⅱ)アルコール依存症 (以下「依存症」という。)の早期発見・対応 (例) ・依存症に係る知識(症状、アルコール依存への危険信号の前兆となる症状)、予防策等) ・航空機乗組員及び客室乗務員が安心して相談できる外部の相談窓口やピアサポート等の環境に係る知識 ⅲ)業務中の乗務員間での常時相互確認の徹底 (例) ・航空機乗組員及び客室乗務員同士による常時相互確認の徹底 ・社会的に期待される役割、立場及び責任の重大性等を踏まえた業務中の適切な行動の徹底 | 即日実施すべき |
| 改正その2 | 航空機乗組員の健康管理に関する基準の一部改正 | ○ 事業者に対し、アルコール依存症等の乗務員を早期に特定するための対策を講じることやアルコールへの依存傾向からの回復を支援すること等を求める。 ○ その他所要の改正を行う。 | (4) 事業者は、アルコール依存症の乗員・客室乗務員や、日常的に飲酒量が多くアルコールへの依存傾向にある乗員・客室乗務員を早期に特定するため、乗員・客室乗務員の飲酒傾向を把握する等の対策を講じるとともに、外部の相談窓口(精神保健福祉センター、保健所等)やピアサポートの活用等により、乗員・客室乗務員が安心して飲酒に関する相談をできる環境を構築すること。 | 即日実施すべき |
| 改正その3 | 運航規程審査要領細則の一部改正 | ○ 副操縦士及び客室乗務員の職務に、健康状態(酒気帯びの有無を含む。)を常に相互確認すること等を追加する。 ○ その他所要の改正を行う。 | b 航空機乗組員及び客室乗務員は、一連の飛行※1前のアルコール検査から乗務を終了するまでの間、他の航空機乗組員及び客室乗務員が酒気帯び状態でないことについて、常に相互確認を行うこと。万が一、酒気帯び等が疑われた場合には、機上において、他の航空機乗組員又は客室乗務員の立会いの下に行うアルコール検知器を使用した検査の実施も含め、酒気帯びの確認を行うこと。 (1) 検査方法 a 航空機乗組員及び客室乗務員は一連の飛行※1前後に、運航管理者、運航管理担当者及び運航管理補助者は航空機との通信に係る業務を実施する前に、整備従事者は整備作業開始前に、アルコール検知器を使用した検査を行うことにより、酒気帯びの有無を確認すること※2。 (新設) c 最少乗組員数が1人の航空機等、b項による相互確認が困難な場合にあっては、航空機乗組員及び客室乗務員は一連の飛行※1後に、目視等により酒気帯びの有無について第三者の確認※4を受けること。当該確認は、顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を含めて総合的に判断するものとする。 (新設) d 事業者の行う飲酒防止対策が有効に機能していないと認められた場合については、b項及びc項の規定にかかわらず、その状況に応じ、航空機乗組員及び客室乗務員に対する一連の飛行※1後のアルコール検知器を使用した検査の実施(抜き打ちによる実施を含む。)を含めた改善措置を航空局安全部安全政策課長(地方航空局が管轄する航空運送事業者にあっては、地方航空局保安部統括事業安全監督官)に提出し、実施すること。 | お好きにどうぞ |
| 改正その4 | 航空機乗組員等のアルコール検査実施要領の一部改正 | ○ 事業者における飲酒防止対策が有効に機能している場合は、業務中における乗務員間の常時相互確認を徹底することにより、一律の乗務後検査を行わなくてよいこととするが、酒気帯び等が疑われた場合には、機上においてアルコール検知器による検査の実施も含めた確認を行うこと等を求める。 飲酒防止対策が有効に機能していないと認められた場合は、その状況に応じ、乗務後のアルコール検知器による検査の実施(抜き打ちによる実施を含む。)を含めた改善措置の提出・実施を求める。 ○ 飛行間のアルコール検査について、飛行間の時間の長さに関わらず、事業者の管理下にあり飲酒の可能性が極めて低い場合には不要とする。 ○ その他所要の改正を行う。 | お好きにどうぞ | |
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000283609
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000283610
を元に作成(一部省略)
実効性欄は、筆者の意見です。
またまた起きた。即日実施すべき改正は、全従業員記名式のAUDITでしょう?
アルコール検査の細かい実施要領なんて、ぐちゃぐちゃいじっててもしょうがない。JALの内容と今回のピーチ社の内容を見ると、典型的な故意犯、飲酒(傾向や量)否認のケース。
AUDITを即日、全「航空従事者」に実施し、高得点者の特別教育を実施すべきである。
改正案に具体的な管理実施が記載されています。この内容は、実質、AUDITの義務化だと思う。
【飲酒傾向の把握、回復支援の方法の例】
・乗員・客室乗務員に対して定期的にAUDIT(WHOの開発したスクリーニングテスト)を行い、15点以上の場合に、労働安全衛生法等に基づき行われる血液検査の結果におけるγGTPやHDLコレステロールの上昇傾向を確認。
私見1)15点以上じゃない。
私見2)”AUDITの虚偽申告”をアルコール検査失念や飲酒有無の虚偽よりも重い処分(制度設計)とする。
検討会や、航空局は、パブリックコメントの結果をきちんと公表するだろうか?
いつ、事業者は、AUDIT実施をすることになり、社内の飲酒者実態を知ることになるだろうか?
アルコール検査の合理化は、AUDIT義務化、点数把握のあとでいいんじゃないだろうか?
-
2026.2.9
「続かない・忘れがち」その体温確認、点呼と切り離されたままで大丈夫ですか。点呼業務と連動する非接触型体温計「東海電子(TD-100)」、運輸安全SHOPで販売開始
-
2025.12.31
航空局の飲酒規制の緩和、決着つかぬまま1年。その間にも起き続ける航空業の飲酒インシデント。義務化開始から6年たって、239件の中身はどんな内容?
-
2025.12.7
-
2025.11.13